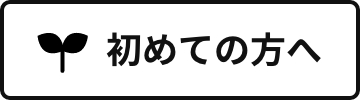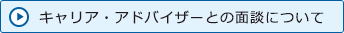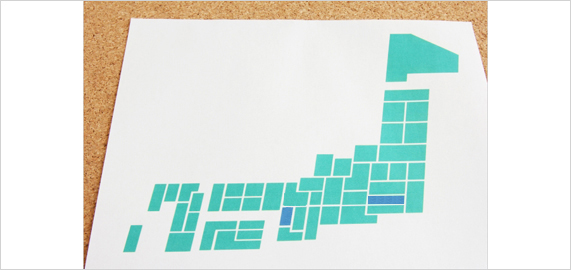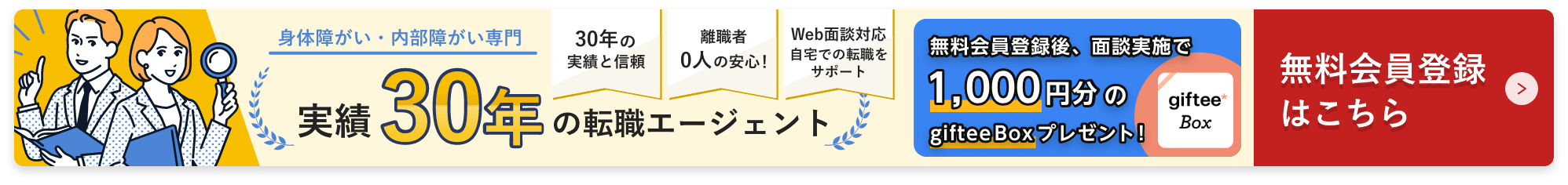勤務時間は配慮すべき項目
障がいによって定期的な通院の必要性が生じたり、通勤時間が余計にかかったりする人も多いと思います。厚生労働省は「障害者のための職場づくりについて望まれること」の一つとして、「障害特性を踏まえた相談、指導及び援助(作業工程の見直し、勤務時間・休憩時間の配慮、援助者の配置等)」を挙げています。
厚生労働省の「平成30年度障害者雇用実態調査」によれば、身体障がい者では、週所定労働時間は、一般的な30時間以上が79.8%と最多で、続いて20時間以上30時間未満が16.4%となっています。また20時間未満の人も3.4%に上る点は考慮すべきでしょう。
知的障がい者では、30時間以上が65.5%と、割合がやや下がり、20時間以上30時間未満が31.4%、20時間未満の人も3.0%でした。精神障がい者では、30時間以上は47.2%、20時間以上30時間未満が39.7%と30時間以上勤務する方との差が他の障がい者より少なくなりました。20時間未満は13.0%と身体障がい者よりも高い割合であることもポイントになります。
募集時間の実態と企業の視点 ~週4日勤務や精神障がい者への時限措置も~
入社する前に、勤務時間の融通が利くか、状況に応じて配慮してもらえるか、確認することが重要です。転職活動者が、勤務時間の条件に重きを置いて、転職先を探す場合、どのような点に気をつければよいでしょうか。
フルタイム勤務とは一般的に、月曜日から金曜日までの週5日勤務のことをいいます。週30時間勤務であれば、1日あたり6時間です。あるいは、週4日で、1日あたり7時間半と設定している企業もあります。定期的な通院回数の多い障がい者は、月に1~2日を通院のための勤務免除日として、雇用契約の中に盛り込んでいるケースもあります。
企業にとっては、週20時間以上30時間未満の人を雇うよりも、週30時間以上の人を雇った方が、法定雇用率の算定が大きくなりますが、精神障がい者に限り、週20時間以上30時間未満でも、雇用開始から3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内であれば、週30時間と同じ換算になる時限措置が2023年まで講じられています。長時間の勤務に不安を抱える精神障がい者にとっては、働く機会が広がり、雇用する企業にとっても、勤務の状況を確認しながら働いてもらえるため、メリットが大きい措置だと言えます。
制度活用に加えて、柔軟に対応可能な場合も ~正直に相談して誠意を示そう~
障がい者の中には、定期的な通院は必要だけれど、土日や夜間に対応している病院に通い、勤務への影響を最小限に抑えている人もいます。その場合は、通院による、平日、フルタイムでの勤務への支障がほとんどありません。
平日に通院するなら、勤務先の規程によって、処遇は大きく変わります。一般的には有給休暇(有休)を取得することになります。半日単位や時間単位で有休を取得できる規程がある会社も増えてきました。短い時間で有休を取れる会社であれば、仕事と通院をより両立しやすくなるでしょう。
また、労働時間の長さや出退勤の時間を労働者自身が決められるフレックスタイム制度があれば、通勤に時間を要する人も、毎日、安心して通うことができます。午前中は通院して、その分、退勤時間を遅らせたり、あらかじめ申請すれば、通院の有無によって、日々の労働時間を変更したりすることも可能です。
さらに、育児や介護などに従事する人の多くが活用する時短勤務や、自宅でも仕事ができる環境を整えることで認められる在宅勤務の制度があれば、仕事への支障を抑えて、より柔軟に対応しやすくなります。
通院に配慮した就業規則を定めている会社も多くあります。たとえば上長など責任者の許可によって、あるいは、緊急かつやむを得ない場合は、業務時間中の通院を認め、その代わり、診断書の提出を義務付けるなどです。
就業規則に通院に関する規程がなくても、通院が絶対に許されないわけではありません。労働法の原則では、プライベートな行為である通院は、原則、業務時間中には許可が下りませんが、やむを得ない事情があれば、まずは、具体的に症状や病状の経過、業務随行の可否、通院日時の予定、仕事に支障を出さないための対応方法や引継ぎについて、よく説明し、会社の許可を得ることも可能です。
障がいによる通院などのために勤務時間への配慮が必要で、転職を希望する場合、まず、自分がどのような働き方をしたいか、具体的にイメージします。1日、あるいは1週間の労働時間と、必要な勤務時間への配慮を書き出し、どうしたら仕事に支障がなく両立できるかを考え、書類や面接で伝えられるようにしておきましょう。
たとえ募集要項に、希望する制度や配慮についての記載がなくても、会社説明会や面接で、採用担当者に確認すると、意外と障がいのある労働者のニーズに合わせ、融通を利かせて対応している場合もあります。障がいの有無にかかわらず、会社には労働者を健康で安全に働かせる「安全配慮義務」があり、また労働者も、自身の健康をきちんと管理する「健康保持(自己保健)義務」があるからです。一次的な情報だけで、勝手に判断せず、まずはしっかりと会社に直接、確認を取りましょう。
きちんと働ける環境を確認してこそ、長く働き続けられる可能性が高まります。障がいに関して、遠慮せず、面接でも正直に相談することで、会社へ働く意欲や誠意を伝えることができるでしょう。